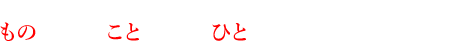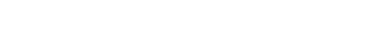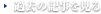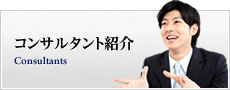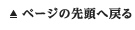- 2023.11.06 かんばんケースなどを発注伝票およびFAXなどでご購入される方(ショッピングサイトを利用しない場合)
- 2023.11.06 かんばんケースの接続方法とフタ
- 2022.11.02 材料費の高騰により、かんばんケースを値上げさせて頂きます
- 2022.11.02 ショッピングサイト構築中
- 2022.09.30 かんばんケースの発送(10/1~10/9まで一時停止)
- 2022.07.07 企業内セミナー(実習)
- 2021.02.17 最近1月から2月まで読まれているコラム ベスト20位
- 2020.07.13 4層不織布フィルターマスクを販売 個人・企業福利厚生 価格改定
- 2023.05.08 地政学を経営に⑱ 面の皮はより厚く腹はより黒く
- 2023.01.19 仕事の4M(人、物、設備、標準)は全て人なり
- 2022.12.01 物づくりの小話し、あれこれ 第122 ネゴシェションとプライス
- 2022.03.18 善は結束するが悪は分裂する
- 2021.02.24 地政学を経営に⑭ 嘘を100回言うと・・・ 国で異なるその後
- 2020.06.15 地政学を経営に⑪ 「欲張りは騙される」
- 2019.09.05 わがままには薄情を
- 2019.05.21 地政学を経営に⑧ 失われた20年が雇用を産む(リメイク2019/7)